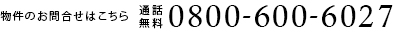ホームポジションの新築住宅が出来るまで
基礎工事編
1.土地の仕入れ
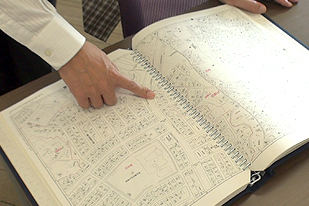
土地情報の収集

社内で分析・検討に入る
2.現地調査とコンセプト作成

現地調査の様子

デザイナーにより物件のコンセプトが作成される
3.地盤調査

【レイリー波表面探査試験】人工振源で表面波速度を測定し、地盤を精度よく推定する

【レイリー波表面探査試験】地盤データを解析中

【スクリューウェイト貫入試験】地中に貫入したロッドと荷重の度合いで、地盤状態を判断

【スクリューウェイト貫入試験】解析データを基に調査報告書が作成される
4.地盤改良

表層改良工事(固化剤を混ぜて撹拌)

柱状改良工事(柱状にセメント材を注入)
【建築士のコメント】
主に3つの改良工事を行っています。軟弱地盤が地面から浅い場合は「表層改良」が行われます。土地を掘削して、セメント系固化材を混ぜて撹拌、転圧することで地盤を固める方法です。深い位置まで軟弱地盤がある場合には「柱状改良」を実施します。掘削しながらセメント材を柱状に注入し、改良杭を作る事で建物を支える方法です。この杭が基礎と地盤を繋いで補強してくれます。さらに深い位置から改良する方法に「鋼管杭工法」があります。鋼管杭を地中の支持層まで貫入し、固い地盤と建物を鋼管杭で支える方法です。
5.基礎着工

砕石・転圧

捨コンと防湿シート
【建築士のコメント】
ランマーを使用して砕石をしっかり転圧し、安定した地盤を形成します。防湿シートには地中の湿気が上がってくるのを防ぐ役割があります。
6.配筋工事

鉄筋同士は結束線でしっかりと固定

配筋工事の様子
【建築士のコメント】
配筋は、本数や位置、高さ、間隔などの基準が設けられています。この基準がしっかりと守られているかどうかは非常に重要で、そのための検査も全ての現場で実施しています。
7.配筋検査

建築士による配筋検査(※)

検査基準に従い厳格に検査します
8.耐圧コンクリート打設

耐圧コンクリート打設の様子

コンクリートバイブレータによる締め固め
【建築士のコメント】
ポイントは、バイブレータを使うことで隅々までコンクリートを充填させる事です。適切な時間で締め固める必要があり、ひび割れや分離などの不具合を防ぐことができます。当社の新築住宅では、コンクリートの強度を24N/mm²(ニュートンパー平方ミリメートル)で統一しています。また、出荷から打設終了までの時間も1時間以内で行っています。これはJIS規格に基づいており、その規格を厳守しています。
9.立ち上がりコンクリート打設

立ち上がりコンクリート打設の様子

均し作業の後、レベラーで仕上げ
【建築士のコメント】
レベラーを使用して基礎天端をきっちりと水平に仕上げていきます。一般的に以前はモルタルが使用されてきましたが、このセルフレベリング材を使用する事で優れた水平精度が確保されます。
10.基礎完成

養生後の型枠撤去作業

きれいな基礎が完成
入念な地盤調査と地盤改良工事、正確な配筋工事と丁寧なコンクリート打設。正確な施工を行う協力業者の方達の腕がホームポジションの新築住宅を支えています。